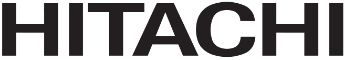現場での注目テーマ
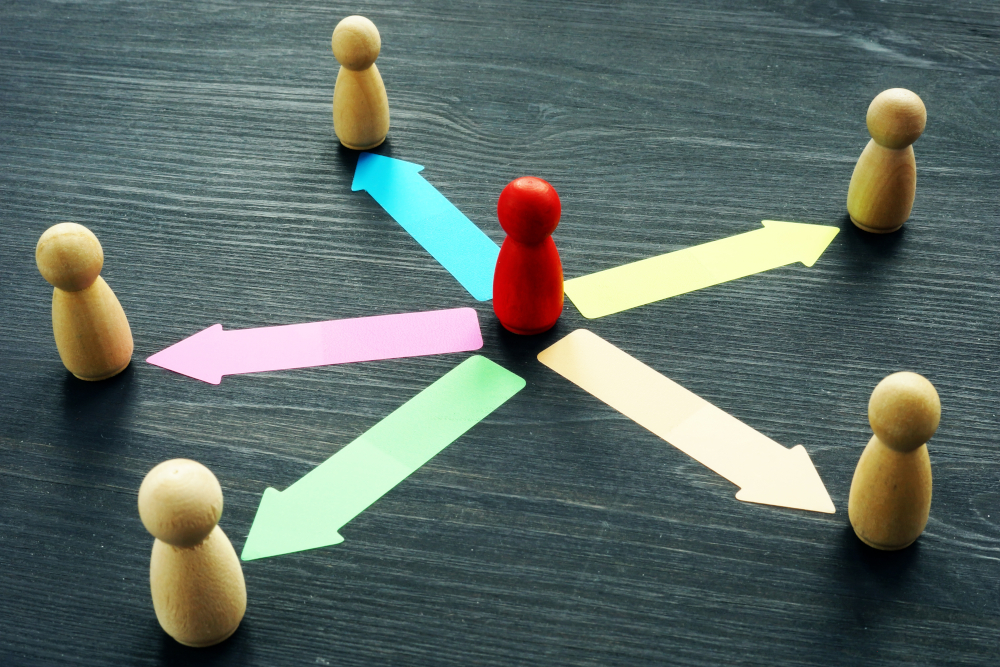
BPOとアウトソーシングの違いは?導入メリット・デメリットについて解説
この記事がオススメな方
主な対象:ファブレス企業、製品メーカー、セットメーカー
- 慢性的な人手不足に悩んでおり、社内の負荷を軽減できる方法としてBPOの活用可能性を探っている方
- 外注や業務改革の選択肢を比較検討するなかで、BPOと他の外部委託手法の違いを知ろうとしている方
近年、深刻な人手不足や業務の高度化に直面する企業が増えるなか、業務効率の改善策として「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」の活用が注目されています。BPOは、単なる外注とは異なり、業務全体を委託することで人材の再配置やコスト削減、品質向上といった効果が期待できます。
この記事では、BPOの基礎から他の外部委託手法との違い、導入のメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
PC・IT機器のフルライフサポートサービス BPOサービスの詳細目次
BPOとは
BPOとは「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略で、特定業務の運用を継続的に委ねる仕組みです。ここでは、BPOの目的や役割、導入が進む背景について解説します。
BPOの目的と役割
BPOは、社内の人的資源や時間を戦略的業務に集中させることを目的とした業務委託手法です。単なる作業の外注ではなく、業務全体の運用を任せることで、業務効率やサービス品質の向上を図ります。
特に専門性の高い分野や間接部門の業務における活用が進んでおり、経営資源の最適化や生産性向上を支える役割を担っています。
BPOの導入が進む背景
人手不足や働き方改革を背景に、企業は限られたリソースを効率よく活用する必要があります。さらに、先行きが不透明なビジネス環境では、新たな人材を採用・育成する余裕がない場面も少なくありません。
また、業務内容が多様化・高度化するなかで、単に作業を代行してもらうだけでなく、業務全体を最適化したいというニーズも強まっています。こうした背景から、企画や改善提案まで担えるような、高度なBPOサービスが求められるようになってきています。
BPOと他手法との違い
BPOは外部委託の一形態ですが、似た手法としてアウトソーシングやシェアードサービス、BPRなども存在します。それぞれの特徴とBPOとの違いを解説します。
アウトソーシングとの違い
BPOはアウトソーシングの一種ですが、委託範囲や目的に違いがあります。一般的なアウトソーシングは、業務の一部を一時的に外部へ任せるのが主流です。一方でBPOは、業務全体を包括的かつ継続的に委託し、課題解決や業務改善も視野に入れた取り組みです。
人手不足への対処にとどまらず、戦略的に外部リソースを活用する点で、より中長期的な視点を持つのが特徴です。
ITO(ITアウトソーシング)との違い
ITOは、情報システムの運用や保守、開発などIT分野に特化した外部委託です。サーバー管理やヘルプデスクなど、技術的な業務が中心になります。
一方、BPOはITに限らず、人事や経理、カスタマーサポートといった多様な業務を対象とし、業務の遂行そのものを外部に任せる仕組みです。IT領域に限定されるITOと比べて、BPOはより幅広い業務に対応する包括的なサービスといえます。
シェアードサービスとの違い
シェアードサービスは、企業グループ内の複数の部門や子会社が、人事・経理などの業務を一か所に集約して処理する仕組みです。業務を担うのは外部企業ではなく、自社内の専門部署やグループ会社の専用組織となります。
一方、BPOは業務全体を社外の専門業者に委託します。どちらも効率化やコスト削減を目的としますが、委託する相手が社内か社外かということに大きな違いがあります。
BPR(業務改革)との違い
BPRとは、自社内で業務プロセスそのものを見直し、大幅な改革を図る考え方です。業務の再設計を通じて、生産性や競争力を高めることを目的とします。
一方でBPOは、外部の専門企業に業務を委託する手法で、業務改革の手段として用いられるケースもあります。最近では、BPRの視点を取り入れた提案型のBPOも増えています。
BPOを導入するメリット
BPOは単なる作業の委託にとどまらず、業務全体の効率や体制そのものに働きかけられる点が特徴です。特に、人材やリソースを戦略的に使いたい企業にとって、有効な選択肢といえます。ここでは、BPO導入によって得られるおもなメリットを紹介します。
人材の再配置による戦略業務への集中
BPOを導入することで、従業員が日々対応していた事務処理や定型作業などを外部に任せられるようになります。その結果、社内の人材を利益や成長に直結するコア業務へ再配置しやすくなり、本来の役割に集中できる体制が整います。
業務の優先順位を明確にし、リソースを戦略的に活用することで、企業全体の生産性や競争力を高められます。
固定費削減と業務リスクの分散
BPOを活用すれば、業務に必要な人材の採用・教育・管理にかかるコストを抑えられます。さらに、設備投資などの初期費用が不要な場合も多く、運用負担の軽減も可能です。業務量に応じて費用が変動する契約を選べば、固定費を変動費化でき、経済環境や繁閑差への柔軟な対応も可能です。
また、業務の一部を外部に分散することで、社内のトラブル時も業務が完全に止まるリスクを避けやすくなります。
業務品質の向上と変化への対応力の強化
BPOでは、専門性の高い業務をプロフェッショナルに任せることで、作業精度や処理スピードの向上が期待できます。特に法改正や技術進化の早い分野では、最新の知識やノウハウを持つ事業者に委託することで、常に適切な対応が可能になります。
自社での情報収集や対応体制を整える負担を軽減し、環境変化への柔軟な対応力を高められることも魅力です。
BPOを導入するデメリット
BPOにはさまざまなメリットがありますが、全ての企業にとって万能な手段とは限りません。外部に業務を委託する以上、注意すべき課題や懸念点も存在します。ここでは、BPO導入時のおもなデメリットを解説します。
ノウハウが社内に蓄積されにくい
BPOでは業務の実行を外部に任せるため、自社に知識やノウハウが残りにくくなります。その結果、将来的に業務を内製化したいと考えた際に、立ち上げや教育に多くの手間やコストがかかる恐れがあります。BPOを導入する際は、情報共有の体制づくりや業務内容を把握し続ける工夫が欠かせません。
情報管理やガバナンス面でのリスク
外部に業務を委託するBPOでは、機密情報や個人データを取り扱う機会も多く、情報漏えいに注意が必要です。たとえ委託先の過失であっても、自社の信用が損なわれる事態になりかねません。そのため、委託先のセキュリティ体制や対応フローを事前に十分確認しておくことが重要です。
BPOの対象業務と導入の具体例
BPOの対象業務は多岐にわたり、経理や人事などの間接業務から、営業支援やコールセンターといった顧客対応業務まで幅広く対応可能です。業務内容によっては、IT系BPOと非IT系BPOに分類されることもあります。
たとえば、採用業務の一括代行や会計処理の外部委託、Webサイトの運用保守などがその一例です。自社の業務特性に合わせた柔軟な活用が可能です。
BPOの委託形態と契約の仕組み
BPOには、外部スタッフが自社に常駐して業務を担う「オンサイト型」と、委託先の施設で業務を行う「オフサイト」型があります。オンサイト型は緊密な連携が図りやすく、オフサイト型はコスト抑制や災害時の事業継続といった面で有利です。
契約面では、成果物の完成を目的とする請負契約、業務の遂行を目的とする準委任契約、法的行為を委ねる委任契約などに分かれます。
| 契約形態 | 概要 | おもな該当業務例 |
|---|---|---|
| 請負契約 | 成果物の完成が目的。結果に対して受託側が責任を負う。 | システム開発、給与計算、Web制作など |
| 準委任契約 | 業務遂行そのものが目的。結果ではなく過程に対する責任を負う。 | コールセンター、運用保守、事務処理など |
| 委任契約 | 法的行為の委託が目的。準委任と同様に遂行義務がある。 | 税務申告、登記、訴訟対応、契約書作成など |
BPOパートナー選定時に確認すべきポイント
BPOの効果を最大化させるには、パートナー選びが極めて重要です。委託先選定時に確認すべき4つのポイントを解説します。
情報セキュリティ・法令遵守への対応状況
BPOでは、個人情報や機密データを取り扱う場面も多いため、委託先の情報管理体制は非常に重要です。ISO27001やプライバシーマークなど、第三者認証の有無は信頼性を測る指標になります。あわせて、法令遵守や内部統制の体制も確認し、インシデント発生時の対応フローまで事前に把握しておきましょう。
事業規模や業務対応範囲の柔軟性
長期的にBPOを活用する場合、委託業務の拡大や変更に柔軟に対応できるかは重要な判断材料です。対応範囲が広く事業規模が大きい企業であれば、業務量の増加にも安定して対応できます。反対に、規模が自社の求める内容に合っていない場合、リソース不足によって業務品質や対応力が確保できない可能性があります。
専門性・対応実績・業界理解の深さ
BPOは専門性の高い業務を任せる場面が多いため、事業者がどの分野に強みを持っているかを見極める必要があります。判断材料としては、実績数だけでなく自社と同業種・同規模の取引経験があるかどうかがポイントです。業務を単にこなすだけでなく、課題の本質を理解し、付加価値を提供できるかが評価の分かれ目です。
費用感とコストバランスの妥当性
BPOを選定する際は、コストの安さだけでなく、提供されるサービスの質とバランスを見ることが重要です。単価が低くても対応範囲や品質が不十分では、かえって業務効率を損なう恐れがあります。複数社から見積もりを取り、期待する成果や体制との費用対効果が見合っているかを慎重に比較検討しましょう。
まとめ
BPOは業務全体を外部に委託する手法で、人手不足や非効率の課題に対応できる有効な選択肢です。類似手法との違いや契約形態を理解し、自社の状況に合わせて導入することが重要です。
リスク対策と信頼できるパートナー選びでは、費用面だけでなくセキュリティや実績、対応範囲などを総合的に見極めましょう。
日立ケーイーシステムズでは、調達からキッティング、設置、保守、データ消去まで、IT機器に関わる煩雑な業務を一括で代行する「BPO・フルライフサポートサービス」を提供しています。人手不足やIT部門の負担に悩む現場でも、最小限のリソースで導入から運用までを効率化できます。まずはお気軽にご相談ください。
PC・IT機器のフルライフサポートサービス BPOサービスの詳細