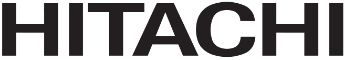現場での注目テーマ

工場の設備管理を変えるIoT活用術|仕組み・導入メリット・事例まで解説
この記事がオススメな方
主な対象:製造業の設備管理
- 老朽化が進む工場設備の故障が相次ぎ、IoTを活用して予知保全を導入できないか調べている設備管理担当者の方
- 業務の属人化や点検の手間に課題を感じ、IoTによる効率化事例や導入手順を探している工場のDX推進担当者の方
老朽化設備の故障や属人化した点検作業に悩む製造現場では、IoTによる情報の見える化と効率化が注目されています。設備の稼働状況をリアルタイムで把握し、異常の予兆を検知できる仕組みは、予知保全や省力化に直結します。この記事では、IoTの基本的な仕組みから設備管理における活用メリット、具体的な導入ステップや事例までを、現場目線で解説していきます。
WORKFRONT/eq目次
IoTとは現場の情報を可視化し活用するための技術のこと
IoT(Internet of Things)とは、モノ同士がインターネットを介して情報をやりとりする仕組みを指します。工場設備にこの技術を導入すると、温度や振動、稼働状況などのデータをセンサーで取得し、リアルタイムで可視化できます。
従来は現場での目視や定期点検に頼っていた管理も、遠隔での監視や分析が可能です。これにより、異常の兆候を早期に把握したり、ムダの多い運用を見直したりと、現場DXを進める重要な基盤となっています。
設備管理・保全業務でDX技術が注目されている背景
工場設備の保全業務では、突発的な故障による生産停止や、属人化による対応のばらつきが課題といわれています。また、保全コストの増大や予算確保の難しさも重荷となり、従来のやり方では限界が見え始めている状況です。
こうした状況のなか、IoTを活用して設備の状態を常時監視し、異常の兆候を早期に捉える「予知保全」の導入が進んでいます。人手に頼らない効率的な保全体制の実現に向け、DX技術の活用が不可欠となっています。
設備管理におけるおもなIoTの活用事例
設備管理の現場では、点検や保守、在庫管理など多くの業務が存在し、属人化やミスによるトラブルも起こりがちです。ここでは、IoTを導入することで、どのように業務が効率化されるのか解説します。
遠隔での設備状態把握による巡視点検の効率化
IoTによって設備の稼働状況を常時モニタリングできるようになれば、目視による巡回点検の頻度を減らせます。たとえば、温度や振動などのデータをセンサーで取得し、異常がない場合は現地確認を省略する運用が可能です。
これにより、巡回業務の効率化や作業負荷の軽減が実現され、少人数でも広範囲の設備を管理できる体制が整います。遠隔地にある複数拠点の状態も一元的に把握でき、緊急時の迅速な対応にも役立ちます。
人的ミスを防ぐための操作状況のリアルタイム監視
設備の誤操作によるトラブルを防ぐため、IoTで操作履歴や稼働データをリアルタイムで監視する現場が増えています。特に複雑な操作が求められる装置では、正しい手順を踏まなければ起動できない制御システムを導入することで、ヒューマンエラーを未然に防止できます。
また、異常な操作があった場合にアラートを発信し、管理者に即時通知する仕組みも有効です。これにより、業務の安全性と品質が大きく向上します。
部品や消耗品の在庫状況を見える化して管理工数を削減
IoTを活用すれば、工場内で使用される部品や消耗品の在庫数をセンサーで自動計測し、リアルタイムで可視化できます。在庫切れによる作業中断や過剰在庫のリスクを防ぎ、必要なタイミングでの適切な補充が可能となります。
また、発注や棚卸作業も自動化できるため、管理工数を大幅に削減可能です。結果として、設備管理の精度が高まり、現場全体の業務効率化にもつながります。
設備管理にIoT技術を取り入れるメリット
IoTの導入は、単なる見える化にとどまらず、現場の効率化や品質向上、コスト削減といった多方面に効果をもたらします。ここでは、設備管理の業務にIoTを取り入れることで得られるおもなメリットを解説します。
人手に頼らず現場の稼働率を高められる
IoTを活用すれば、分散した設備の稼働状況を遠隔で把握できるため、人手による巡回や確認作業の負担を大幅に削減できます。その結果、少人数でも安定した稼働体制を維持でき、生産計画の乱れも防げます。突発対応や属人化のリスクも抑えられるため、人手不足や急な離職にも柔軟に対応可能です。持続的かつ効率的な運用体制を実現することは、現場全体の生産性向上にもつながります。
人件費・エネルギーコストを抑えたスマート運用の実現
IoTにより設備の稼働状況やエネルギー使用量を見える化できれば、不要な稼働やムダな消費を抑えた最適運用が可能になります。特にピーク時の電力使用を平準化することで電気料金を削減でき、設備ごとの運用効率も向上します。
加えて、巡回や点検の自動化により人手にかかるコストも抑えられるため、全体として運用コストの低減と環境負荷の軽減を同時に達成できることは大きなメリットです。
不良の兆候を検知し、安定した品質を維持できる
センサーを通じて温度や振動などの変化を常時監視することで、製品の品質に影響を及ぼす異常の兆候を早期に察知できます。従来は見逃されがちだったわずかな変化も検出可能になり、不良品の流出を未然に防止できます。
生産プロセスの安定性が高まり、品質のばらつきを抑えられるため、クレームや手直しにかかる負担の軽減も可能です。結果として、顧客満足度の維持・向上にもつながります。
トラブルを未然に防ぐ予兆検知と計画保全ができる
IoTにより設備の状態を継続的に記録・蓄積しておくことで、異常値の傾向や変化パターンからトラブルの兆候を事前に捉えやすくなります。これにより、想定外の故障や生産ライン停止といった重大インシデントを回避でき、突発的な対応に追われる運用から脱却できます。
定期点検に加えて、必要な時だけ無駄なく整備を行えるため、安定稼働の確保とメンテナンスコストの最適化を同時に実現可能です。
リアルタイム分析による即応体制を構築できる
IoTで取得した稼働データをリアルタイムで分析できれば、現場で起きている変化を即座に把握し、迅速な意思決定につなげられます。過去の勘や経験に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて最適な対応策を選択できるようになるため、対応ミスや判断の遅れを回避可能です。
変化が激しい現場においても、的確な判断と即応力を両立した運用体制を構築できることは大きなメリットといえます。
IoT導入で現場を変えるまでの実践プロセス
IoTは導入すればすぐに結果が出るわけではなく、現場課題の整理や運用設計が欠かせません。やみくもにセンサーを設置しても成果にはつながりにくいため、目的に応じたステップを踏むことが重要です。ここでは、IoT導入を現場改革につなげるための具体的なプロセスを解説します。
非効率な業務や見えないムダを洗い出す
IoT導入の第一歩は、現場の業務を見直し、どこにムダや非効率が潜んでいるかを把握することです。設備点検の手間や重複作業、トラブル時の対応遅れなど、現場で当たり前となっている業務のなかに改善余地が隠れています。
まずは現場担当者の声をもとに課題を洗い出し、それらが業績や品質に与える影響の大きさを評価することで、IoT化によって解決すべき優先度の高い対象を明確にできます。
IoTで解決できるポイントを具体化する
課題が見えてきたら、それをIoTでどう解決できるかを具体的に検討します。たとえば「異常の見逃しが多い」という課題に対しては、温度や振動のセンサーでリアルタイム監視を行うことで対処できます。単にデータを集めるのではなく、どの業務をどう変えたいのかを明確にし、必要な情報を整理することが重要です。目的と手段を明確にすることで、現場に合ったIoT活用が実現しやすくなります。
必要な情報とセンサー選定の考え方を整理する
解決策が明らかになったら、次は「何のデータが必要か」「どうやって集めるか」を考えるステップです。取得したい情報が温度・湿度・稼働時間・電力量なのか、それによって使うセンサーの種類や設置方法も変わります。
必要以上に多機能なセンサーを選ぶと、コスト過多になり、逆に精度不足では意味をなしません。課題に直結するデータだけを効率よく取得できるよう、現場環境に合わせた選定が求められます。
集めたデータを分析し施策へつなげる
IoTで得たデータは、収集するだけでは意味がありません。重要なのは、そこから何を読み取り、どのように業務改善につなげるかという点です。たとえば、故障頻度と温度変動の関係性を分析し、故障予防のタイミングを明確化すれば、ムダなメンテナンスを減らすことも可能です。
点としてのデータを、時間軸や他機器との相関で捉えることで、施策の根拠を可視化でき、再現性の高い改善サイクルが構築されます。
まとめ
IoTは設備の稼働状況を把握し、異常の兆候を検知することでトラブルやムダを減らす技術として注目されています。設備保全の現場では属人化や突発的な対応といった課題を改善する手段として導入が進み、点検作業の効率化や予防保全の実現にも役立っています。
設備保全の属人化を解消し、計画保全やノウハウの共有をシステムで効率的に実現したいという場合は「WORKFRONT/eq」をぜひご活用ください。保全台帳の電子化や履歴管理、設備ごとの保全計画の自動作成など、保全業務の全体最適化を支援します。
さらに、複数工場の管理統一や部品共通化、保全実績の見える化といった多拠点展開にも強みを持つシステムです。詳しくは以下のページをご覧ください。
WORKFRONT/eq