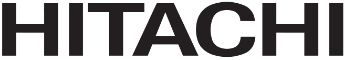現場での注目テーマ

製造現場の効率化を高めるDX活用術|導入メリットと成功のポイントを解説
この記事がオススメな方
主な対象:製造業の開発部門、サービス部門
- 自社の現場業務に限界を感じていて、DXの導入効果や成功事例を調べている製造部門の責任者
- DX推進を任され、製造業での推進ステップや課題を整理したいと考えている企画・情報システム担当者
人手不足や業務の複雑化が進むなか、製造業ではDX(デジタルトランスフォーメーション)による抜本的な現場改革が急務となっています。工程の効率化にとどまらず、組織の競争力を高める手段として注目されているDXですが、導入には明確な戦略と継続的な取り組みが欠かせません。
この記事では、製造業DXの基礎知識から導入の効果、実践事例、推進のステップまで解説していきます。
日立ケーイーシステムズの稼働監視サービスWORKFRONT/CLOUD
目次
製造業におけるDXとは
製造業のDXは、単なるデジタル化ではなく、業務や組織のあり方を根本から見直す変革です。顧客ニーズの多様化や技術革新のスピードが増すなか、競争優位を維持するためにも、継続的な改善と柔軟な対応力が求められています。ここでは、その必要性と現状について解説します。
製造業におけるDXの必要性
製造業でDXが求められる背景には、経営環境の激変や人材不足、国内市場の縮小、老朽化したシステムの課題などがあります。特に近年は、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)が高まる「VUCA時代」とも呼ばれ、企業には柔軟かつ迅速な対応が求められています。
こうした状況を乗り越え、競争力を維持するには業務変革と基盤強化が欠かせません。
製造業におけるDXの現状
製造業のDXは一部では進んでいるものの、業界全体では導入の遅れが目立ちます。実際、2021年時点でDXに未着手の企業は7割以上に上り、業界全体としては過渡期にあるといえるでしょう。
人手不足や品質改善といった現場課題の解決策として、IoTやAIなどの技術導入が進みつつありますが、戦略設計や体制整備は依然として課題となっています。
※参考:令和3年版 情報通信白書|我が国におけるデジタル化の取組状況|総務省
製造業DXで重点的に取り組むべき3つの領域
製造業のDXは、単なる一部業務の効率化にとどまらず、企業全体の構造を変革する取り組みです。なかでも「バリューチェーン」「サプライチェーン」「エンジニアリングチェーン」の3領域は、成果に直結する中核的な対象とされ、重点的な対応が求められます。ここでは、それぞれの特徴と取り組みの視点について解説します。
バリューチェーンのDX|製造工程全体の流れの最適化
バリューチェーンとは、原材料の調達から製造・販売・アフターサービスに至るまで、製品が価値を生む一連の流れを指します。この全体像をDXで見直し、プロセス間の連携強化や業務の効率化を図ることで、付加価値の最大化が可能になります。
AIによる需要分析やデータに基づく業務改善が中核となるでしょう。
サプライチェーンのDX|調達から供給までの仕組みの強化
サプライチェーンとは、製品を作るための資材調達から生産、在庫管理、配送といった供給に関わる一連の流れです。
DXを活用してこの流れを最適化することで、需要変動や供給リスクに柔軟に対応できます。IoTによるリアルタイム監視やAIによる需給予測が、持続可能な供給体制の鍵を握ります。
エンジニアリングチェーンのDX|設計から製造までの連携強化
エンジニアリングチェーンとは、製品の企画・設計から試作・製造に至る前の開発工程を指します。DXによってこれらのプロセスをつなぎ、設計と製造現場の情報共有をスムーズにすることで、開発スピードや品質が大幅に向上します。デジタルツインによる検証や自動化技術の導入が改革の軸となるでしょう。
製造業DXで得られる3つの効果
DXにより現場が大きく変われば、経営や組織運営にも多面的なメリットが生まれます。ここでは、生産性の向上、意思決定の強化、競争力の底上げという3つの効果について解説します。
業務の効率化と新たな価値創出
製造業では、AIやIoT、RPA(Robotic Process Automation)の活用により、業務の自動化が進み、現場の省力化と迅速な意思決定が可能になります。
これにより生産性が向上するだけでなく、データを基にした新たな製品やサービスの創出といったビジネスモデルの転換も期待されています。効率化と価値創出の両立こそがDXの本質といえるでしょう。
データと人材の最適活用による経営強化
製造工程の可視化や各種センサーによるデータ取得が進むなか、現場情報を生かした経営判断が重要性を増しています。予測型の生産計画やトラブル検知は、従来の属人的な判断を補完し、的確な投資や人材配置を後押しします。データと人材を結びつけた運用は、組織の強さの底上げにつながります。
標準化と組織の柔軟性による競争力向上
業務が標準化されると、技術継承が進み、教育や配置転換も円滑に進められます。また、変化に強い柔軟な体制が整うことで、市場環境への対応力が高まります。こうした組織の機動性は、市場変化への即応力となり、企業の優位性を高める要因となるでしょう。
製造業DXを阻む3つの課題
DXの重要性が広く認識される一方で、製造業では思うように進まない現場も少なくありません。その背景には、組織や体制に関わる根本的な問題が潜んでいることが少なくありません。ここでは、経営・投資・人材といった面で多くの製造企業が直面する課題について解説します。
経営ビジョンや戦略が定まっていない
DXを進めるには、技術の導入だけでなく「何のために変革するのか」という明確なビジョンが欠かせません。目的が曖昧なままでは、施策が部分的にとどまり、全体の成長につながりません。まずは経営層が方向性を示し、全社で共有することが重要です。
全体戦略のなかでDXの位置づけを明確にすることが、成功の第一歩となるでしょう。
設備投資の意思決定が難しい
製造業のDXは、多額の設備投資を伴うことが少なくありません。そのため、投資対象や優先順位の判断が難航しがちです。現場の課題や将来の収益性を踏まえて、投資判断の根拠を明確にする必要があります。
公的支援の活用や段階的な導入を検討することで、無理のない形でDXを進めやすくなります。
DXを担う人材の確保と育成が進まない
DXには、現場理解とデジタルスキルの両方を持つ人材が不可欠ですが、慢性的な人手不足が課題となっています。採用強化や外部人材の活用だけでなく、社内の人材に対して新たな知識や技術を学び直す機会を設けることも重要です。
特に現場をよく知る従業員は、育成次第で即戦力として活躍できる可能性が高いといえます。教育体制を整え、長期的に人材を育てる姿勢が、DXの土台を支えることにつながります。
製造業DXを成功させる進め方
製造業のDXを成功させるには、技術の導入だけでなく、戦略や人材、運用体制を含めた全体設計が不可欠です。現場だけで完結させるのではなく、経営との連携や継続的な改善プロセスを意識することが、定着と成果につながります。ここでは、製造業のDX推進の基本ステップについて解説します。
DXの目的と戦略を一貫性のある形で設計する
DXは、企業としての目的やビジョンと結びついた全体戦略があってこそ成果が見込めます。何を目指すのか、どの領域で価値を生むのかを明確にし、段階的な計画に落とし込むことが重要です。方針が定まれば、各部門の施策もブレにくくなり、組織一体での推進が実現しやすくなるでしょう。
必要な人材・スキル・体制を整える
製造業のDXでは、デジタルに強い人材がいればよいというわけではありません。たとえば、工場設備のIoT化を推進するには、現場工程に精通した従業員とIT部門が連携し、互いの知見を掛け合わせる体制が不可欠です。
また、3D設計やデジタルツインに対応できるスキルの明確化と育成が重要です。こうした役割やスキルを具体的に定義し、業務と紐づけて整理することで、採用や育成の方針も現実的なものになります。
実行後の成果を見直して改善を継続する
製造業のDXは、一度の導入で完成するものではありません。たとえば、生産ラインに導入したAI画像検査が期待通りに動作しない場合、その要因を洗い出し、再学習やライン設定の調整を行う必要があります。
こうした運用上の改善を、KPIに基づいて迅速に回すことで、現場に根付くDXへと進化します。変化を前提とした設計が重要です。
製造業DXの成功事例に学ぶ実践のヒント
DXを実現するには、自社に合った手法を見極めることが重要です。とはいえ、具体的な導入イメージが湧かないという声も少なくありません。その場合は、先進企業の事例からヒントを得るのが有効です。ここでは、実際の製造業のDX事例について解説します。
設計・生産・知見を融合したデジタル基盤の構築事例
ある工作機械メーカーでは、設計と製造部門の間でCADや生産管理システムのデータをリアルタイムで連携させ、設計変更が即座に製造工程に反映される仕組みを構築しました。さらに、現場で蓄積された加工ノウハウやトラブル対応例も社内データベース化し、他部署と共有します。結果として、工程全体の可視化と部門間連携の強化につながり、生産効率と品質の向上を実現しています。
既存データを生かしたIoTプラットフォームの活用事例
ある大手製造企業では、各工場に分散していた3D設計データや設備の稼働ログをIoTプラットフォームに集約し、設計・生産・保守の各部門で情報を共有できる体制を整えました。これにより、不具合の原因分析や保守作業の迅速化が可能となり、トラブル対応にかかる時間が短縮しています。結果として、現場の負荷軽減と稼働率の安定につながっています。
まとめ
製造業のDXでは、業務単位の改善にとどまらず、設計から生産・保守までをつなぐ全体的な最適化が重要です。 経営戦略と連動した仕組みづくりに加えて、人材や体制の整備も欠かせません。課題は多いものの、段階的な戦略設計と継続的な見直しによって、現場に根付いた変革が可能になります。
設備の状態を的確に把握し、サービス対応の効率化を進めたい場合は「WORKFRONT/CLOUD」をご活用ください。稼働データをもとに出動判断や保守作業の質を高めるだけでなく、ダウンタイムの削減やサービス品質の改善にもつながります。まずは下記ページをご確認ください。
WORKFRONT/CLOUD