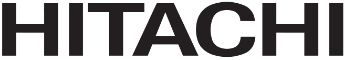現場での注目テーマ

製造業のDXはなぜ進まない?7つの理由と推進を成功させる5つのステップを解説
この記事がオススメな方
主な対象:製造業の生産管理・生産技術・設備管理・品質保証
- 製造業の情報システム部門の担当者や、経営者が自社のDXを進めようと旗を振っている方
- なかなか現場の協力が得られずに思ったように進捗しないため、その理由を知りたい方
自社の「製造業DXが進まない」と頭を抱えている人もいるでしょう。企業がこれから厳しい競争を生き抜く上で、DXの推進は不可欠です。しかし、計画通りに進んでいる企業は限られています。
本記事では、製造業DXが進まない理由について詳しく解説します。また、成功させるためのステップや成功事例にも触れるので、DX推進の担当者や代表者は最後までご覧ください。
WORKFRONT/PF製造業DXとは?
製造業DXとは、IoTやAI、クラウドといった最新のデジタル技術を活用し、従来の製造プロセスやビジネスモデルそのものを変革させる取り組みです。単に紙の書類を電子化したり、特定の工程にITツールを導入したりする「デジタル化」とは異なります。
製造業におけるDXには、既存業務の効率化やコスト削減を目的とする「守りのDX」と、新たな製品やサービスを創出して収益向上を目指す「攻めのDX」の2つの側面があります。
製造業におけるDXのゴール
製造業がDXを推進した先にはどのようなゴールがあるのでしょうか。ここでは3つの視点で解説します。
スマートファクトリーの実現
スマートファクトリーの実現とは、工場内の設備や生産ラインにIoTセンサーやAIカメラなどを導入し、データを収集・可視化して、生産プロセス全体を最適化する取り組みです。
リアルタイムで稼働状況をモニタリングし、収集したデータを分析して、非効率な工程の特定や短時間の設備停止の原因究明を行います。省人化や生産性の向上が期待できます。
新たな価値提供
製造業におけるDXは、生産効率の改善だけでなく、新しい製品やサービスを生み出し、新たな価値の提供も重要なゴールです。
たとえば、製品にIoTセンサーを組み込めば、顧客の使用状況をリアルタイムで収集し、故障予知や遠隔メンテナンスといった付加価値の高いアフターサービスを展開できます。付加価値を高めることで、製品やサービスへの満足度を間接的に高められるでしょう。
サプライチェーンの最適化
サプライチェーンの最適化は、デジタル技術を用いて原材料の調達から生産、在庫管理、物流、販売に至るまでの一連の流れを可視化し、全体最適を図る取り組みです。
各拠点に散らばっていた資材や在庫、納期といった情報をIoTやクラウドシステムで一元管理し、関係者間でリアルタイムに共有して、部門間の連携を強化します。
製造業でDXが進まない理由
メリットは多いものの、DXが進まない企業が多いのが現状です。ここでは製造業でDXが進まない理由について見ていきましょう。
ビジョン・目的の欠如
製造業でDXが進まない理由の1つが、経営層におけるビジョンや目的の欠如です。DXを「最新ツールの導入」と捉え、導入自体が目的化してしまい、何を達成したいのかという具体的な目標が設定されていないケースが多く見られます。経営層がDXの真の価値や必要性を十分に理解していなければ、全社的な協力体制は築けません。
人材不足
DXを推進するためには、ITやデータサイエンスの専門知識と、製造現場の業務プロセスの両方を深く理解した「橋渡し役」となる人材が不可欠です。
多くの製造業企業では、双方のスキルを兼ね備えたデジタル人材が不足しています。また、デジタル人材は市場価値が高く、採用競争も激しいため、外部から人材を確保するのは困難です。
コスト・予算の壁
DX推進には、IT機器やソフトウェア、ロボットの導入に多額の初期投資が必要です。システムの維持管理やアップデートにかかるランニングコスト、従業員への教育費用なども発生します。
また、DXへの投資はすぐに利益に結びつくとは限らず、費用対効果が不明瞭であるため、経営層が投資に踏み切れないケースもあります。
レガシーシステムの問題
多くの製造業では、長年にわたって使い続けてきた独自の基幹システムや生産管理ツール、いわゆる「レガシーシステム」が稼働中です。特定の業務に合わせて作り込まれているため、複雑化・ブラックボックス化が進んでいます。レガシーシステムが足かせとなり、全社的なデータ活用や業務プロセス変革が困難になっています。
現場の抵抗と無関心
現場の抵抗感や無関心もDXが進まない理由のひとつです。製造現場では、長年培ってきたアナログな手法や従来の業務プロセスへの信頼が厚く、「これまでこのやり方で問題なかった」「新しいやり方は面倒だ」といった変化への抵抗感が根強く存在します。
現場が「また余計な仕事が増える」と捉え、経営層との対立構造に陥る場合もあります。
組織・文化の課題
組織全体の文化や体制に問題があり、DXが進まない場合も珍しくありません。DX推進を担う専門部署が存在せず、誰が主導するのか曖昧なまま計画が立ち消えになるケースもあります。
紙の帳票や口頭での情報伝達が主流のアナログ文化な組織では、データに基づいた意思決定の習慣が醸成されていないため、DXの浸透が進みません。
業界構造の問題
日本の製造業は、諸外国と比較してデジタル化の取り組みが遅れている傾向にあります。個々の企業の課題だけでなく、業界全体の構造的な問題も一因でしょう。
製造業は、部品メーカーから組み立てメーカー、販売店まで、多くの企業が関わる複雑なサプライチェーンで成り立っているため、一社単独でDXを進めても効果が限定的になりがちです。
製造業DXを成功させる5つのステップ
製造業のDXは、ツールを導入すれば成功するわけではありません。ここでは、DXを成功に導くための具体的な5つのステップを紹介します。
1.明確なビジョンと目的を策定する
DXを推進するなら、「なぜDXに取り組むのか」というビジョンと目的の明確化に取り組みましょう。
「生産性を30%向上させる」「新たなサービスで売上を10%伸ばす」といった具体的な目標を設定し、手段としてDXを位置づけます。策定したビジョンと目的は、全従業員に分かりやすい言葉で共有し、組織全体で目指すべき方向性を統一しましょう。
2.優先順位を決める
明確なビジョンが描けたら、次に取り組むべき課題に優先順位をつけます。「効果が大きい」「導入の難易度が低い」といった観点から、着手しやすいものから始めましょう。
従業員がメリットを実感しやすく、かつ費用対効果が高いテーマを優先的に選べば、DXへの機運を高め、次のステップへとつなげやすくなります。
3.成功体験を積む
優先順位の高い課題からスモールスタートで取り組み、小さな成功体験を積みましょう。帳票の電子化によって特定の業務の残業時間が削減された、設備の稼働データ可視化で不良品の原因が特定できた、といった具体的な成果を目指します。
成功体験を積めば、DXに懐疑的だった現場従業員の意識を変え、「やればできる」という前向きな雰囲気につながります。
4.DX推進体制の構築と人材育成
DXを継続的に推進するには、専門の推進体制の構築が不可欠です。経営層、IT部門、そして製造現場の各部門からメンバーを集めた横断的なプロジェクトチームを組成し、全社的な旗振り役を担わせます。
特定の担当者だけに依存するのではなく、現場の誰もが当たり前にデジタルツールを使いこなせるような教育体制と仕組みも大切です。
5.効果測定と評価、全社展開
DXは、システム導入で終わりではありません。導入後にその効果を定期的に測定・評価し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回し続けましょう。
スモールスタートで得られた成功モデルとノウハウを標準化し、他の部署や工場へと段階的に展開していけば、最終的に全社的なDXの実現につながります。
製造業DXの成功事例3選
国内の製造業においても、DXに成功し成果を上げている企業もあります。ここでは具体的に3つの成功事例について見ていきましょう。
生産性向上・品質改善
あるメーカーでは、紙で運用していた作業日報や点検表を電子化したところ、従来1日2時間かかっていた作業をわずか数分に短縮しました。
また、別のメーカーでは、拠点ごとにバラつきがあった作業品質を安定させるため、動画マニュアルを導入し生産性を数十%も向上させています。工程内不良率を3分の1まで削減した部品メーカーの例もあります。
技術伝承・人材育成
熟練技術者が持つ技能やノウハウの伝承は、多くの製造業にとって喫緊の課題です。ある部品メーカーでは、動画マニュアルと自社開発のシステムを連携させた教育の仕組みを構築し、作業の標準化と技能伝承を進めています。
動画マニュアルで、紙の手順書では伝わりにくい「カン・コツ」といった暗黙知を、誰にでも分かりやすく可視化しました。
新たな価値創出
DXは、既存業務の効率化にとどまらず、新たなビジネスモデルを創出する原動力にもなります。IoT技術を活用して自社製品の使用状況を遠隔でモニタリングし、予知保全や最適な運用方法の提案といった、新たなアフターサービスを展開する企業もあります。
また、AIを用いて市場データや顧客の声を分析すれば、新しい製品やサービスの開発につなげられます。
まとめ
製造業DXが進まない理由には、ビジョン不足、人材やコストの課題、レガシーシステム、現場の抵抗感など、複数の根深い問題が横たわっています。本記事で紹介したDXを成功させるためのステップを参考にすれば、DX推進が可能となるでしょう。
自社でのDX推進が困難な場合は、日立KEの製造業様向けIoTシステム開発ノウハウをフレームワーク化した「WORKFRONT/PF」をご検討ください。オーダーメイドのIoTシステムの開発でありながら、コストや開発期間の削減を実現しています。以下のリンクより詳細をご確認いただけます。
WORKFRONT/PF