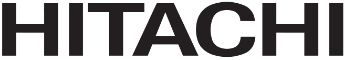現場での注目テーマ

予防保全とは|種類と効果、導入時の注意点や計画づくりのポイントを解説
この記事がオススメな方
主な対象:製造業の設備管理
- 設備の故障や品質低下を防ぐため、予防保全の種類や効果、導入時の注意点をまとめて知りたいと考えている方
- 工場や施設で予防保全を検討しており、計画の立て方やスケジュール作成のポイントを調べている方
予防保全は、設備の故障やトラブルを未然に防ぎ、生産効率や品質を安定させるために欠かせない取り組みです。実施方法にはさまざまな種類があるため、工場や設備の状況に合わせた計画を立てましょう。この記事では、予防保全の目的や分類、導入による効果に加え、実践時に押さえるべき注意点やスケジュール作成のポイントを解説します。
WORKFRONT/eq予防保全とは
予防保全とは、設備や機械の故障を未然に防ぐために、あらかじめ点検やメンテナンスを計画的に行う取り組みです。
具体的には、決めた周期で部品を交換したり摩耗や劣化を確認する作業を指します。稼働中の異音や温度上昇など、状態異常を定期的にチェックすることも含まれます。ここでは、予防保全の役割や保全予防などとの違いについて解説します。
予防保全の目的と役割
予防保全の目的は、設備や機械の故障を未然に防ぎ、生産性や品質を安定させることにあります。突発的なトラブルを防ぐことで、生産停止や納期遅延といった損失を避ける役割を担います。
また、定期的な点検や部品交換を計画的に実施し、安全な作業環境を維持し、従業員を守ることも予防保全の役割です。これらは、企業全体の収益にも直結します。
事後保全や保全予防との違い
予防保全は、設備を運用するなかで故障を未然に防ぐための保全措置を講じる手法です。一方、事後保全は、故障が発生した後に、修理や交換を行う方法で、突発的な停止リスクが高まります。
また、保全予防は、設備設計の段階で信頼性や保全性を高める工夫を盛り込む考え方です。つまり、予防保全は運用段階での対策、保全予防は設計段階での対策という点が大きな違いです。
予防保全の主な分類と特徴
予防保全には決まった周期で行う方法や、設備の状態や使用状況に合わせて実施する方法など複数の種類があります。設備特性に合った手法を選ぶことが大切です。ここでは、予防保全の主な分類と特徴を解説します。
時間基準保全|定期スケジュールで実施する保全方法
時間基準保全(TBM)は、決められた周期に基づいて定期的に点検や部品交換を行う予防保全手法です。設備の稼働時間や状態にかかわらず、あらかじめ設定したスケジュールで保全を実施します。
計画通りに作業を進められるため管理しやすい反面、まだ使用可能な部品を早めに交換するケースもあり、コストが高くなる可能性があります。使用状況が安定している設備に有効な手法です。
状態基準保全|設備状態の変化を基準に行う保全
状態基準保全(CBM)は、設備の状況を定期的に測定し、その結果に基づいて保全時期を判断する手法です。摩耗、振動、温度、異音などのデータを収集し、劣化の兆候を見極めて必要な作業だけを行います。
時間基準保全のように無駄な部品交換が減る一方で、適切な測定項目や点検の頻度を決める必要があり、導入時にはセンサーの設置やデータ管理体制の整備が求められます。
予知保全|データ分析で故障発生を予測して対処
予知保全(PdM)は、IoTセンサーやAI、機械学習などの技術を活用し、設備の異常を高精度に予測する手法です。リアルタイムで収集したデータを分析し、故障が発生する前に必要な保全を行います。状態基準保全を高度化した方法であり、無駄なメンテナンスを抑えつつ突発故障のリスクを最小限にします。
ただし、過去の故障データや分析モデルの構築が不可欠で、導入には一定の初期投資が必要です。
故障発見保全|小規模な不具合を早期に発見・対処
故障発見保全(FFM)は、普段は動作が見えにくい機器や安全装置が、必要なときに正常稼働するかを確認する保全手法です。非常用発電機やスプリンクラー、無停電電源装置など、使用頻度は低いですが、重要な設備で活用されます。
時間基準保全と基本的に同じですが、対象が「非常時だけに動く装置」に限られる点が違いです。試験運転や機能確認を通じて、緊急時の不具合を未然に防ぎます。
利用基準保全|使用回数や稼働時間を基準に実施する保全
利用基準保全(UBM)は、設備の使用回数や稼働時間など、実際の利用状況を基準にしてメンテナンス時期を決める手法です。コピー機の印刷枚数や車の走行距離のように、使用量の記録をもとに保全スケジュールを設定します。
過剰な交換を防げる一方、利用データを正確に収集する仕組みが必要です。センサーや管理システムを導入する場合が多く、初期コストや分析体制の準備も考慮する必要があります。
予防保全のメリットと企業にもたらす効果
予防保全を導入すると、設備の安定稼働や品質向上など、企業にさまざまな効果が期待できます。ここでは、製品品質や稼働率、コスト管理、設備投資などの観点から、予防保全がもたらす主なメリットを解説します。
製品品質を安定的に確保できる
設備が劣化した状態で稼働を続けると、不良品の発生や品質低下につながる恐れがあります。予防保全を実施することで、故障や異常が起こる前に点検・交換を行い、設備を常に最適な状態に保てます。結果として、製品品質のばらつきを抑え、安定した供給が可能になります。
品質維持は顧客からの信頼向上にもつながり、リピート率の向上や新規顧客の獲得にも効果を発揮します。
稼働率を高め停止時間を最小化できる
予防保全を行わずに故障が発生すると、修理対応や部品調達に時間を要し、生産ラインが長期間停止しかねません。定期的な点検や部品交換を計画的に実施すれば、突発的なトラブルを大幅に減らせます。その結果、製造現場の稼働率が向上し、納期遅延などのリスクを最小限に抑えられます。
安定した供給体制を確保できれば、取引先からの信頼性も高まり、企業全体の評価を上げることも可能です。
保守部品や消耗品の在庫を最適化できる
突発的な故障が多いと、非常時に備えて多くの予備部品を抱える必要があり、在庫コストが膨らみます。予防保全を実施すれば、交換時期をあらかじめ把握できるため、必要な部品を必要な分だけ計画的に準備できます。結果として、保守部品や消耗品の在庫を最適化し、保管スペースや在庫管理にかかるコストも削減可能です。
効率的な在庫管理は資金繰りの安定にも寄与し、企業全体の経営改善にもつながります。
設備寿命を延ばし投資効果を最大化できる
設備が故障すると、故障か所以外にも過大な負荷がかかり、寿命を縮める原因になります。予防保全を実施し、劣化部品を早めに交換することで、設備への負担を減らし、長期的な安定稼働を実現できます。設備更新までの期間が延びるため、新たな投資を抑えることによるコスト削減も可能です。
設備を最大限に活用できることで投資対効果(ROI)が高まり、経営資源の有効活用につながります。
予防保全の際に注意したいこと
予防保全は多くのメリットをもたらす一方で、導入や運用には複数の課題も存在します。ここでは、具体的な注意点について解説します。
作業負担が増える可能性がある
予防保全では、設備に異常がなくても定期的な点検や部品交換を行う必要があります。そのため、事後保全や予知保全と比べて保全作業の回数が多くなり、現場の工数や担当者の負担が増える傾向があります。特に複数の設備を管理する場合は、スケジュール調整や作業準備にも時間がかかります。
作業効率を落とさないためには、対象設備や点検内容を見直し、適切な頻度で実施する工夫が欠かせません。
維持・運用に一定の費用が発生する
予防保全は、突発的な故障を防ぐ効果がある一方で、維持や運用に一定のコストがかかります。定期的に部品を交換するため、まだ使用できる部品まで早期に取り換える場合があり、オーバーメンテナンスによるコスト増加が課題となりがちです。
また、点検作業に必要な人件費や設備を測定するためのセンサーなど、導入時の初期投資も発生します。効果とコストのバランスを意識した保全計画が重要です。
計画通りに進められない場合がある
予防保全は、計画通りに実施することを前提としていますが、現場では必ずしも思い通りに進むとは限りません。点検時期と繁忙期が重なると作業時間の確保が難しくなったり、部品の調達が遅れて保全計画がずれたりするケースもあります。
さらに、現場担当者の経験や勘に頼って点検時期を決めていると、最適なタイミングを外すリスクもあります。保全計画は柔軟性を持たせ、定期的に見直すことが大切です。
予防保全を適切に行うためのスケジュールとルールの作り方
予防保全を効果的に進めるには、まず設備ごとの重要度や故障リスクを分析し、優先順位を明確にすることが大切です。生産に与える影響が大きい設備から順に重点的な点検や整備を行うことで、限られたリソースを効率的に活用できます。
次にメーカー推奨のメンテナンス周期や実際の稼働状況に基づき、点検や部品交換のスケジュールを策定します。さらに、作業ミスを防げるように点検項目や作業手順を標準化し、担当者に共有しましょう。
最後に、実施後は効果を定期的に評価し、計画を見直すことでより最適な保全体制を維持できます。
まとめ
予防保全は、設備の故障を未然に防ぎ、生産性や品質を安定させるための重要な取り組みです。効果を最大化するには、設備ごとの重要度を見極め、計画的な点検や交換を進める必要があります。現場全体で保全方針を共有し、無駄のない体制を整えることが重要です。
効果的な保全管理を実現するには、デジタルツールの活用が効果的です。弊社サービス「WORKFRONT/eq」であれば、設備台帳の電子化から保全計画の自動作成まで一括でサポートしています。費用面でも導入しやすいパッケージですので、まずは下記資料をご覧ください。
WORKFRONT/eq