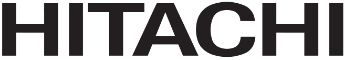現場での注目テーマ

IoT予知保全とは?予防保全との違いや導入する際のメリット・デメリットを解説
この記事がオススメな方
主な対象:製造業の設備管理
- 予知保全とは何か、予防保全との違いは何か知りたい方
- IoTを活用した予知保全の方法を知りたい方
- IoTを活用した予知保全の課題やデメリットを知りたい方
こんにちは。現場の最適化を実現するソリューション「WORKFRONTシリーズ」で、品質向上・生産性向上・省エネ推進をご支援する日立ケーイーシステムズのライターチームです。
製造業をはじめとする多くの業界では、設備や機器の安定稼働が生産性や品質の維持に欠かせません。しかし、従来の設備保全方式では、無駄なコストの発生や突発的な故障への対応といった課題がありました。こうした背景から、近年ではIoT技術を活用した新しい設備保全方式『予知保全』が注目を集めています。
今回は、IoTを活用した予知保全の仕組みや導入する際のメリット・デメリット、システム導入までの流れを初心者向けにわかりやすく解説します。予防保全や事後保全との違いを知り、設備保全の効率化を図りましょう。
WORKFRONT/eq設備保全における課題
従来の設備保全では、稼働中の機械を一定の期間ごとに停止し、点検や修理などのメンテナンス作業を行う必要があります。そのため、メンテナンスの度に生産ラインが一時的に停止され、生産性の低下を招く原因となっていました。実際には故障していない部品にも交換や修理を施すため、メンテナンスコストがかさむというデメリットもあります。
加えて、設備のコンディションを正確に把握するには多くの人手が必要であり、設備によってはリアルタイムの稼働状況を監視するのが難しいケースもあります。このように、設備保全ではさまざまな課題が浮き彫りとなっているのが現状です。
設備保全の課題を解決する予知保全とは?
予知保全とは、IoT技術を用いて設備の稼働状況や劣化状況を常時モニタリングし、将来的な故障を予測した上でメンテナンスを行う新たな設備保全方式です。これによって設備の停止を最小限に抑えることができ、必要なタイミングで適切な修理やメンテナンスを実施できます。予知保全は従来の定期点検や突発的な故障対応に比べてメンテナンスコストを削減でき、設備の安全性も高く保持できるとして近年注目を集めています。
予防保全との違い
予知保全と似た設備保全方式に、予防保全があります。予知保全と予防保全は名前が似ていることから混同されがちですが、両者はメンテナンスを行うタイミングが明確に異なります。
予防保全は、設備の故障リスクを減らすために、設備の寿命や使用回数に基づいて計画的に点検や交換を行う方法です。この方式はメンテナンス計画を一元化できますが、設備の実際の劣化状態を正確に反映できず、必要以上にメンテナンスを行ったり、まだ使用可能な部品を早期に交換したりと、コストや工数の無駄が発生することもあります。一方で予知保全は、IoT技術を活用して必要なタイミングでのみメンテナンスを行うため、メンテナンスにおける無駄を最小限に抑えることができます。
事後保全との違い
事後保全は、設備が完全に故障してから修理を行う方法です。最もシンプルな保全手法といえますが、突発的な停止による生産ラインへの影響が大きく、修理コストや納期の遅延リスクが高まります。
これに対して予知保全は、事前に設備の異常兆候を察知し、計画的に保全対応を行えます。予知保全は、従来の事後保全からの脱却を目指す上での効果的な選択肢といえます。
IoTを活用して予知保全を行うメリット
IoTを活用して予知保全を行うことで、生産性の向上やコストカットなどのさまざまなメリットが得られます。
設備故障の防止によって生産性を上げられる
IoTを活用した予知保全では、センサーが設備の振動・温度・音などのデータを常時収集し、異常の兆候をいち早く検知できます。これによって設備故障による突発的な生産ラインの停止を防止でき、安定した生産体制を維持できます。生産性を向上させることで、企業全体の業績にも好影響を与えられるでしょう。
設備停止を最小限に抑えられる
IoTを活用した予知保全によって、設備の状態に基づいた適切なタイミングでメンテナンスを実施できます。これまで課題だった長時間の計画停止や緊急対応の必要がなくなり、設備の稼働時間を最大化できるため、生産スケジュールへの影響が減少し、生産管理がスムーズになるでしょう。
メンテナンスコストを削減できる
IoT技術によって設備の状態を常時把握することで、必要なときだけ効率的にメンテナンスを行う体制を構築できます。従来のような定期点検での過剰保守が不要となり、部品交換やメンテナンス技術者にかかるコストを大幅に削減できるでしょう。必要以上のメンテナンスをなくしながらも、設備の安全性を維持できるのが予知保全の大きな魅力です。
技術者の負担を軽減できる
従来の手作業による設備保全作業では、技術者が日々の点検や異常検知に多くの時間を割いていました。IoT技術を活用した予知保全では、IoTセンサーがリアルタイムで設備状況を監視してくれるため、作業の大部分を自動化でき、作業効率が大幅に向上します。技術者の負担を軽減できるのも、予知保全方式のメリットの1つです。
メンテナンスの属人化を解消して品質を保全できる
IoT技術によって設備の稼働状態が数値で可視化されることで、メンテナンスを行う技術者の経験や勘に頼らない保全が可能になります。技術者への属人化が解消されることで、設備保全業務の標準化が進み、作業品質を安定化できるでしょう。
IoTを活用して予知保全を行う際のデメリット・注意点
IoTを活用した予知保全には多くの利点がある一方で、導入時に注意すべき点もあります。
IoTを活用する環境を整備する必要がある
設備保全においてIoTを活用するためには、監視センサーなどのIoTデバイス・通信ネットワークの整備・データを蓄積・分析するインフラの構築などが必要です。特に既存の設備が古い施設では、IoTを導入するための環境整備にコストがかかるケースもあり、導入ハードルが高いというデメリットがあります。
IoT技術者やデータ分析者の確保が難しい
IoT技術によって収集された膨大な設備保全データを分析し、的確な状況判断を行うには、専門知識を持った人材の登用が必要不可欠です。しかし、現在の市場ではIoTの技術者やデータサイエンティストが不足しており、人材の確保に課題が生まれています。IoTや予知保全を導入する際は、人事面での戦略を練る必要もあります。
アラートの基準設定が難しい
IoTを活用した予知保全では、設備に設置したセンサーが異常を検知した際にアラートを通知することができます。しかし、アラートの精度にはまだ課題があり、場合によっては重大な故障リスクを見逃したり、厳しい基準によって誤検知が多発したりする可能性もあります。正確なアラートシステムを整備するためには、運用データの蓄積と検証を繰り返しながら、最適な基準値を調整する必要があります。
事後保全からの切り替えに手間がかかる
従来の「設備が故障してからメンテナンスを行う」という考え方の事後保全から、「設備が故障する前兆を検知して事前にメンテナンスを行う」という考え方の予知保全へと移行するには、業務フローの見直しや新たなシステムの導入、従業員への教育などのさまざまな切り替え準備が必要です。円滑な設備保全方式に移行するためには、万全の計画準備や現場の理解が欠かせません。
導入コストがかかる
IoTによる予知保全の導入には、センサーをはじめとしたIoTデバイスの設置・ネットワークの構築・クラウドサービスの利用料・業務システムの開発など、多くの初期投資が必要になります。特に大規模な設備保全の改革には大きなコストがかかるため、予算の確保や事前の運用シミュレーションが必要不可欠です。
予知保全システム導入の流れ
予知保全システムを導入する際は、まず現状の設備保全における課題を明確にし、どの設備のどのデータ項目を計測したいのかを洗い出す必要があります。続いて、必要な機器の取り付けやネットワークの整備を行い、設備保全データの収集環境を構築します。導入前には従来の設備保全方式からの業務フローの刷新や従業員への教育を行うことも重要です。場合によっては、本格的な運用を開始する前に試験運用を行うという方法もあります。
<システム導入の流れ>
- 解決したい課題や必要なデータ項目の策定
- 導入する監視カメラや監視センサーの選定
- 機器の調達
- ネットワーク設定・予知保全システムの構築
- 稼働環境の準備・従業員への受け入れ教育
- 運用開始
- 運用状況分析・改善
まとめ
IoTを活用した予知保全は、従来の保全方式では難しかった設備状態のリアルタイム監視や故障予測を取り入れることができ、より効率的な設備保全を可能にします。予知保全を行うことで無駄なメンテナンスコストや人件費を削減できるうえ、設備の稼働率も大幅に向上できます。一方で、システム導入に際しては、専門知識を持つ人材の確保や、従来の設備保全システムからの移行など、いくつかの課題が存在します。予知保全のメリットとデメリットを正しく理解した上で、自社の状況に応じた導入計画を立てることが重要です。
日立ケーイーシステムズでは、設備保守をトータルで支援するシステム「WORKFRONT/eq」を展開しています。設備台帳の電子化・保全実績入力・履歴管理・保全計画の自動作成などのサポートを行っているので、設備管理の省人化や異常検知の効率化を目指す現場担当者は、ぜひご利用を検討ください。
WORKFRONT/eq