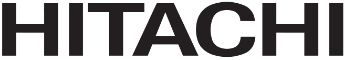現場での注目テーマ

業務効率化を実現する物品管理の基本とメリット|実施手順をわかりやすく解説
この記事がオススメな方
主な対象:ファブレス企業、製品メーカ、セットメーカ
- 物品の所在や数量が把握しづらく、棚卸しや在庫確認に時間がかかっているため、効率的な物品管理の方法を探している方
- 在庫管理システムは導入しているが、備品や共有物品の管理まではカバーできず、台帳整備や社内ルールの作り方を調べている方
物品管理は、担当者ごとのやり方に頼ると情報の共有が難しくなり、紛失や記録漏れなどのリスクが高まります。特に手作業での管理は、確認作業に時間がかかり、在庫過不足や重複購入といった非効率さを招きやすい傾向があります。
台帳を整備し、分類や保管ルールを明確にすることで、現場の混乱を防ぎ、業務全体をスムーズに進められます。この記事では、物品管理の基本や導入によるメリット、効果的な実施手順について解説していきます。
PC・IT機器のフルライフサポートサービス BPOサービスの詳細物品管理とは
物品管理とは、社内の備品や消耗品などを適切に把握・維持するための仕組みです。ここでは、物品管理の目的や重要性、在庫管理との違いについて解説します。
物品管理の目的と重要性
物品管理は、備品や消耗品、機材などの所在・数量・状態を正確に把握し、必要に応じて更新や修理を行う仕組みです。これにより、紛失や重複購入、故障による業務停滞を防げます。資産状況を明確にすることで、適切な会計処理や節税にもつながります。
さらに、社内外への情報漏えいリスクや不正利用を防止し、内部統制を強化する役割も果たします。効率化・コスト削減・セキュリティ向上を同時に実現できるという点で、企業にとって欠かせない仕組みといえます。
在庫管理との違い
在庫管理と物品管理はいずれもモノを管理しますが、対象や目的が異なります。物品管理は、社内で使用する机や棚、パソコン、重要書類、鍵、文房具などを対象に、状態や所在を把握して適切に維持します。
一方、在庫管理は販売する商品や製造資材を対象に、入出庫や数量を最適化することが目的です。前者は内部資産の維持管理に重点を置き、後者は外部への安定供給を確保する点で重要なものです。
物品管理のメリット
物品管理を行うことで、業務環境や経営面にさまざまな効果が期待できます。ここでは、そのなかでも代表的なメリットを解説します。
業務効率化につながる
物品の所在や貸出状況がすぐにわかれば、探す時間や確認作業が減り、業務をスムーズに進められます。会議や作業の準備も短時間で整えられ、担当者間での引き継ぎも簡単です。情報を一元化することで部署をまたいだ共有が進み、現場対応のスピードが向上します。
結果として日々の業務負担が軽減され、より重要な業務に集中できる環境が整うでしょう。
コストの無駄を削減できる
正確な数量や使用状況を把握していれば、在庫があるのに追加購入してしまうといった無駄を防げます。遊休品や使われない備品の放置も減らせ、廃棄コストや保管スペースの浪費を抑制可能です。さらに、資産台帳を整備して減価償却を適切に行えば、税務面での損失も避けられます。
長期的には調達費用や人件費の削減にもつながり、経営の健全化にも寄与します。
常に最適な物品状態を維持できる
物品の状態を定期的に点検すれば、不具合や故障を早期に発見し、業務への影響を最小限に抑えられます。必要な時に必要なものが稼働可能な状態でそろっていれば、作業効率が高まります。保守や修理の計画も立てやすくなり、突発的な買い替えや作業中断のリスクが減少します。結果として、安定した業務の運営が可能です。
セキュリティ面でのリスクを抑えられる
物品の管理が不十分では、社外への持ち出しや紛失により、機密情報や顧客データが流失する危険性があります。物品管理を導入すれば、誰がいつ何を持ち出し、どこに保管しているかを明確にできます。特にノートパソコンやUSBメモリなどの情報媒体は、適切な管理によって不正利用や情報漏えいを大幅に低減できます。企業の信用維持にも直結する重要な効果です。
内部統制の強化につながる
物品の所在や数量が正確に把握されていれば、不正な持ち出しや私的流用を防ぎやすくなります。管理ルールを定めて運用すれば、全社的な資産管理体制が強化され、監査対応や証跡提示もスムーズです。内部統制の一環として物品管理を組み込むことで、経営資源の透明性が高まり、ガバナンス強化に貢献します。結果として、組織の信頼性と安定性が向上します。
物品管理の基本ステップ
物品管理は、単にモノの出し入れを記録するだけではありません。正しい段取りで進めることが、現場の混乱を避け、効果を着実に出す上で重要です。ここでは、物品管理の基本的なステップについて解説します。
1.まずは物品管理台帳を整備する
物品管理を活用する上ではじめに行うのが「台帳の作成」です。Excelやクラウド型の管理システムなど運用方法を決め「管理番号・物品名・種別・数量・購入日・保管場所・利用状況・状態」などの基本情報を項目化します。
初期登録では現場と照合しながら漏れなく入力し、保証書や説明書などの関連資料も紐づけると後の管理がしやすくなります。更新担当者と頻度を決めて、異動や新規購入時の反映ルールを明文化しておくことで、運用開始後も精度の高い管理が続けられます。
2.物品を分類してラベルで明確化する
登録した物品は、消耗品・機材・備品など大枠で分けた上で、使用頻度・利用部署・設置場所などで細かく分類します。分類後は管理番号や名称、使用期限、貸出制限などを記載したラベルを作り、現物に貼ります。
バーコードやQRコードを導入すれば、棚卸しや貸出・返却の際にスキャンで情報更新が可能です。ラベルの色分けや大型機材への目立つタグ付けなど視覚的な工夫を加えることで、探す時間を減らし、紛失や誤使用の防止にもつながります。
3.保管場所や配置ルールを決める
物品は利用頻度や重要度、サイズを考えて最適な保管場所を決めます。よく使う文具や消耗品は手に取りやすい場所に置き、高価品や機密物は施錠できる保管庫や入退室管理のある部屋に置きます。倉庫では棚番号やゾーン分けを行い、ラベルや案内図と連動させると探しやすくなります。
配置は一度決めたら固定し、移動が必要な場合は台帳やラベル情報をすぐに更新しましょう。こうしたルールを明文化し、全員に共有できれば整理状態を長く保ちやすくなります。
4.定期的に棚卸しを行う仕組みをつくる
棚卸しは、台帳の情報と現物が合っているかを確認するために欠かせない作業です。月ごとや四半期ごとなど定期スケジュールを決め、数量や状態、使用期限を点検します。棚卸表を事前に準備し、担当者に割り振れば、作業が効率的に進みます。
不足や余剰が見つかればその場で台帳を修正し、補充や廃棄を判断します。結果は管理責任者や経理部門と共有し、改善点を反映させることで不正防止や資産管理の精度向上につながります。
5.管理ルールを社内に周知・徹底する
物品管理は担当部署だけでなく、利用する全員が関わります。貸出・返却の方法や記録更新の手順、緊急時の対応などをまとめたマニュアルを作成し、掲示板やイントラネットで常に確認できるようにしておきましょう。
従業員研修や定期ミーティングでルールを説明し、問題があればすぐに改善します。ルールは定期的に見直し、業務内容や組織変更に合わせて更新することで、全員が参加する安定した管理体制を保てます。
物品管理を効率化するポイント
物品管理は、担当部署だけでなく利用する全員が関わる業務です。仕組みがうまく回らなければ、紛失や業務停滞といった大きな問題に直結します。ここでは、現場での管理をよりスムーズに進めるための効率化ポイントについて解説します。
位置情報をリアルタイムで共有する仕組み
物品にRFIDやGPS機能付きICタグを取り付ければ、位置情報を自動で記録できます。これにより、探し回る手間や長時間の棚卸作業が不要になり、持ち出し先や保管場所をシステム上で即時に確認可能です。工場内の工具やイベント備品など、頻繁に移動する物品の所在管理にも有効で、紛失リスクを大幅に低減します。
ネットワーク経由で複数拠点間の情報共有も行えるため、全社的な在庫可視化が実現します。
管理台帳に写真や図を添えて視覚化する
数字や文字だけの台帳では、類似品や型番違いの見分けが難しく、ミスの原因になりがちです。物品ごとに写真や図面を添付すれば、名称だけでは判別しづらい物品も一目で特定できます。特に大型備品や特殊工具などは、外観画像があるだけで棚卸しや貸出時の確認が格段にスムーズです。
紙やExcel台帳では添付に限界があります。クラウド管理システムなら画像やPDFも簡単に保存・共有でき、現場での確認作業を効率化できます。
スマートフォンで簡単に情報を更新できる環境を整える
バーコードやQRコード入りの管理ラベルを貼れば、スマートフォンやハンディスキャナーで読み取るだけで台帳情報を呼び出せます。外出先や倉庫でもその場で状態や数量を更新でき、情報の遅れや漏れを防ぎます。棚卸しも端末をかざすだけで完了し、システムが自動で照合してくれるため、現物と台帳を突き合わせる手間が不要です。
紙や口頭での申告を減らすことで、記録ミスや属人化の防止にもつながります。
業務負担を減らすならシステム導入がおすすめ
物品管理システムを導入すれば、所在や状態の把握、棚卸作業などを自動化でき、手作業に比べて工数を大幅に削減できます。バーコードやICタグを読み取るだけで、登録や在庫確認、履歴管理まで一元化できるため、記録漏れやミスも防止可能です。管理者の負担を減らし、現場の効率を飛躍的に高められます。
まとめ
物品管理は、所在や状態を正確に把握し、効率的な運用を続けるために欠かせない取り組みです。台帳整備や分類、棚卸しの仕組み化を徹底すれば、紛失や重複購入を防ぎ、業務の生産性を高められます。さらにシステムや外部サービスを活用することで、管理負担の軽減や精度向上も実現可能です。
日立ケーイーシステムズでは、パソコン・IT機器のフルライフサポートサービスやBPOサービスを通じ、物品管理を含む幅広い業務の効率化を支援しています。自社の管理体制を一歩進めたい場合は、ぜひ以下のサービス詳細をご覧ください。
PC・IT機器のフルライフサポートサービス BPOサービスの詳細