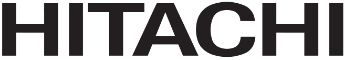現場での注目テーマ
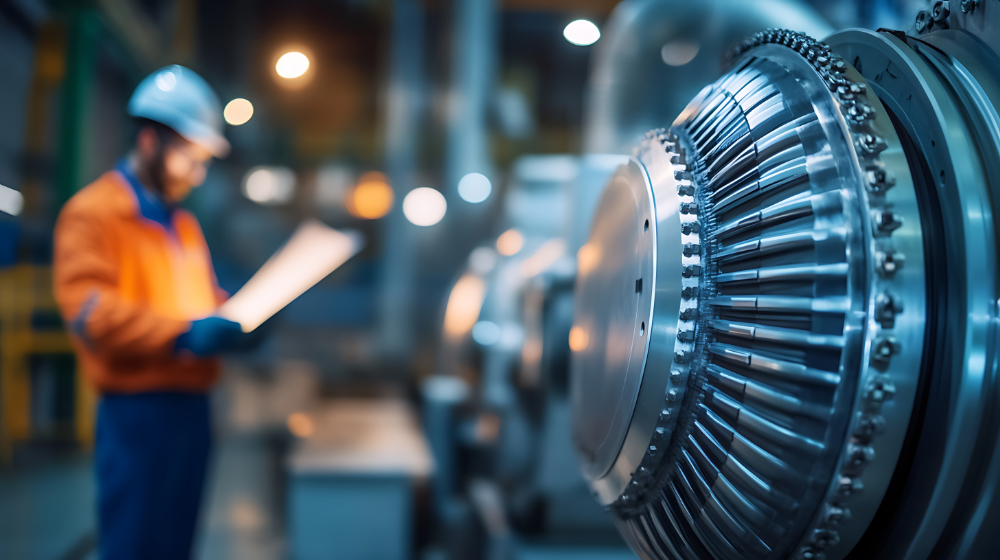
設備保全とは?保守・メンテナンスとの違い、IoT活用まで解説
この記事がオススメな方
主な対象:製造業の設備管理
- 設備保全とは具体的にどのようなものなのか、保守やメンテナンスとの違いを知りたい方
- 設備保全を効率的に行う方法を知りたい方
- 設備保全に関する最新技術を知りたい方
こんにちは。現場の最適化を実現するソリューション「WORKFRONTシリーズ」で、品質向上・生産性向上・省エネ推進をご支援する日立ケーイーシステムズのライターチームです。
設備保全は、工場の安定稼働と生産性向上に不可欠です。一方で、業務の属人化や人手不足、コストの増大といった設備保全に関する課題に直面している製造現場も少なくありません。
本記事では、設備保全の基本的な定義や目的、具体的な種類について解説します。企業が抱える課題や、IoTやAIを活用した設備保全にも述べるため、ぜひ最後までご覧ください。
mcframe SIGNAL CHAIN設備保全とは?
まずは設備保全に関する基本的な言葉の定義と、混同されがちな保守・メンテナンスとの違いについて解説します。
設備保全の定義
設備保全とは、工場の生産設備や機械が故障せず正常な状態で稼働できるように維持し、性能を最大限に引き出すための計画的な活動を指します。
具体的には、日常的な点検、定期的な部品交換や修理、設備の劣化状態を監視・予測してトラブルを未然に防ぐ活動などが含まれます。故障を予防し、設備の長寿命化を図ることで、安定した生産体制を維持します。
保守との違い
設備保全と保守は範囲に違いがあります。保守は、設備が正常な状態を維持できるよう、点検や修理、清掃といった「現在の機能を維持するための作業」というニュアンスが強い言葉です。
一方、設備保全は、保守活動に加えて、将来の故障を防ぐための計画立案や、設備の性能を改善するための改良活動までを含む、広い範囲の概念と捉えられます。
メンテナンスとの違い
メンテナンスは、英語で維持・持続を意味する言葉であり、日本語の保守とほぼ同義で使われます。日常的な点検や部品の交換、清掃・給油といった、設備の機能を維持するための作業です。
実務上、保守とメンテナンスは明確に区別されずに使われる場合が多いものの、どちらも設備保全の一部といわれています。
設備保全の目的
設備保全の目的は、単に故障を防ぐことにとどまりません。ここでは、代表的な3つの目的について詳しくご紹介します。
生産性の維持・向上
設備保全の最大の目的は、設備の突発的な故障による生産ラインの停止を防ぎ、生産性を維持・向上させることです。計画外のダウンタイムは、生産計画の遅延を引き起こし、納期遅れによる顧客からの信頼失墜や機会損失につながります。定期的な点検や計画的な部品交換を行い、設備の安定稼働を確保し生産量を確保しましょう。
製品品質の維持・向上
生産設備の性能や状態は、製品の品質に影響を与えます。設備の摩耗や劣化を放置すると、加工精度が低下したり、動作が不安定になったりして、不良品の発生率が高まります。
設備保全を通じて、設備を最適な状態に保ち、製品品質のばらつきを抑えて、安定した品質を維持しましょう。品質の安定は、企業の競争力を高める上で重要な要素です。
安全な作業環境の確保
設備の老朽化や整備不良は、時に労働災害を引き起こす原因となります。機械の誤作動や部品の破損などが起これば、現場で働く従業員が危険に晒されかねません。
設備保全は、リスクを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける安全な作業環境を確保する目的も担っています。定期的な安全点検や危険か所の改善を徹底し、安全配慮義務を果たしましょう。
3種類の設備保全
設備保全は、アプローチ方法によって大きく3つの種類に分類されます。ここではそれぞれの保全について解説します。
予防保全
予防保全は、設備が故障する前に、あらかじめ計画されたメンテナンスを行う手法です。予防保全には2種類あり、1つは時間基準保全です。設備の使用時間や稼働回数など、一定の期間を基準に部品交換やオーバーホールを行います。
もう1つは状態基準保全です。設備の振動や温度などを監視し、劣化の兆候が見られた段階でメンテナンスを行う方法です。
事後保全
事後保全は、設備が故障したり、性能が低下したりした後に、修理や部品交換を行う手法です。故障が発生してから対応するため、生産停止は避けられず、ダウンタイムが長くなるリスクがある一方で、部品コストを抑えられるというメリットもあります。
故障しても生産全体への影響が少ない設備や、交換が容易な部品などに対して採用されます。
予知保全
予知保全は、予防保全を進化させた手法です。IoTセンサーを設備に取り付け、稼働状況を24時間365日リアルタイムで監視します。収集された膨大なデータをAIが分析し、通常とは異なる微細な変化から故障に至る予兆を検知します。
高精度な予測により、部品の寿命が尽きる前の最適なタイミングでのメンテナンスが可能です。
設備保全の課題
多くの製造現場では、設備保全に関する課題に直面しています。ここでは、おもな課題について詳しく解説します。
業務の属人化
業務の属人化は、特定の技術者に、設備保全業務が依存してしまっている状態です。異音や振動の微妙な変化から不具合の原因を特定するといった「暗黙知」は、マニュアル化が難しく、担当者がいなければ対応できないという事態に陥りがちです。担当者の不在時や退職時に、業務が停滞するリスクを抱えています。
熟練技術者の不足と高齢化
人口構造の変化により、製造業ではベテラン技術者の高齢化と、次世代を担う若手人材の不足が深刻な課題となっています。 前述の業務の属人化と相まって、ベテランが退職すると、培われてきた保全ノウハウが失われかねません。
技術継承がスムーズに進まなければ、組織全体の保全スキルが低下し、設備の安定稼働が維持できなくなります。
増え続ける保全コスト
工場全体の設備が老朽化していくにつれて、故障の頻度が増加し、修理費用や交換部品のコストは増大していく傾向にあります。
特に、計画性のない事後保全に頼っていると、突発的な故障による生産停止の損失に加え、緊急対応のための割高な部品調達や人件費が発生し、保全コストが経営を圧迫する大きな要因となるのです。
非効率な情報管理
点検記録や修理履歴、交換した部品の情報などを、紙の帳票やパソコン上のExcelファイルで管理しているケースは少なくありません。情報の所在が分かりづらく、必要な情報を探すのに時間がかかることがあります。また、担当者以外には情報の保管場所が把握されていないケースも見受けられます。
過去のトラブル事例やノウハウが組織全体で共有・活用されず、同じような故障が繰り返し発生する原因にもなっています。
設備保全を成功に導く手順
効果的な設備保全は、計画的なサイクルに基づいた活動が大切です。ここでは、設備保全を成功に導くための5つのステップを紹介します。
1. 設備管理台帳の作成
まず、管理対象となる設備に関する情報を「設備管理台帳」として一元化します。台帳には、設備の名称や型番、製造番号、導入年月日、設置場所、仕様書といった基本情報から、過去の修理履歴、点検記録、交換部品などを記録しましょう。
設備管理台帳は、保全計画を立案し、活動を管理していく上での全ての基礎となります。
2. 保全計画の立案
次に、設備管理台帳の情報を基に、具体的な保全計画を立案しましょう。どの設備を、いつ、誰が、どのような方法で保全するのかを明確にします。設備の重要度や故障時の影響度、過去のトラブル履歴などを考慮して、優先順位を決めましょう。
優先順位に基づき、年間の保全スケジュールや予算を策定し、計画的で効率的な保全活動の土台を築きます。
3. 保全活動を実行
立案した計画に従って、実際の保全活動を実行します。オペレーターによる日常点検や保全部門による定期点検、外部業者への修理依頼などが含まれます。
作業を行う際は、必ず安全手順を遵守し、計画通りに作業が進んでいるかを確認しながら進めてください。計画外の突発的な故障が発生した際にも、すぐに対応できる体制を整えておきましょう。
4. 結果・実績を報告
実行した保全活動の内容は、報告書としてまとめます。いつ、どの設備に、どのような作業を行い、何が原因で、どのような部品を交換し、どれくらいの時間と費用がかかったのか、といった実績データを正確に残しましょう。
実績データは、後の分析や評価において重要な情報となります。現場で簡単に入力できる仕組みを整えると効率的です。
5. フィードバック
収集した実績データを分析し、計画と比較して評価を行います。計画通りにコストや時間内で作業が完了したか、保全活動によって実際に故障が減少したか、といった効果を検証します。
評価結果を基に、より効率的な保全方法はないか、点検の周期は適切か、といった観点から、次回の保全計画の見直しや改善を行いましょう。
設備保全とIoT・AI活用
属人化や人手不足といった課題を解決し、設備保全活動を高度化する切り札として、IoTやAIといったデジタル技術の活用に期待が寄せられています。
具体的には、設備にIoTセンサーを取り付け、24時間リアルタイムで収集したデータをAIで解析します。解析結果に基づき故障が発生するタイミングを予測し、「予知保全」を実現可能です。
ベテラン技術者の経験や勘といった暗黙知も可視化・形式知化できるため、技術継承問題の解決につながります。
まとめ
本記事では、設備保全の定義や目的、種類、多くの現場が抱える課題とそれを乗り越えるための手順について解説しました。設備保全は、単なるコストではなく、企業の生産性、品質、安全性を支え、競争力を維持・向上させるための重要な「投資」です。
まずは自社の現状を把握し、設備管理台帳の整備から始めるなど、できることから一歩ずつ取り組んでみましょう。
自社だけでの設備保全が難しい場合は、株式会社日立ケーイーシステムズの「mcframe SIGNAL CHAIN」をご検討ください。計画・制御・実行の各レイヤーのデータを統合し現場のデジタルデータの利活用を、多方面でサポートします。
mcframe SIGNAL CHAIN